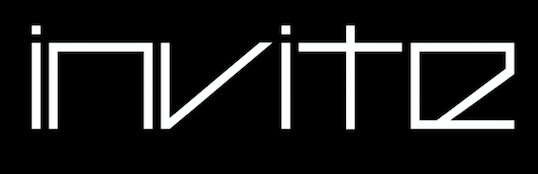日曜の午前10時。
西区姪浜駅の前に車を止めた男は、少し窓を開けてタバコに火を付ける。
待ち合わせの時間は10時15分なので、車内でタバコを吸っても、換気をすれば、問題はないと思っていた。しかし、そんな彼の予想に反して、タバコに火を付けたところで、後方から一人の女性がやってきた。
慌ててタバコの火を消して、携帯灰皿に入れる。
「あ、すみません。少し時間があったんで」
バツの悪そうな表情を浮かべて謝罪する男の名は『白木 裕』。
福岡市内にあるシステム会社に勤める28歳である。
「私が時間ギリギリに来る女だと思ってたの?」
悪戯に笑い、車に乗り込んだ女性は、裕の上司の『早田 沙耶』。
年齢は裕の3つ上で今年で31歳となった。

「いや、そういうわけじゃないですけど」
歯切れの悪い返答をしながら、裕はシートベルトを締め直して車のハザードを消した。
「うそうそ、別に吸えばいいのに。あなたの車なんだから」
一見、傍から見れば二人はカップルに見えるだろう。
しかし、二人はまだ友達以上恋人未満の関係である。
いや、正確には同僚以上恋人未満といった方が正しいかもしれない。
正直、裕もどうして休日に上司と二人で出かけているのか不思議に思っていたのだが、それもそのハズ。
先月末に行われた会社の飲み会のとき、裕が酒に酔ってしまった時、以前から男性として意識していた沙耶が、自身も酒の勢いで裕をデートに誘って今日と言う日が成立していたからだ。
姪浜駅を出た後、裕は都市交に乗り、前原インターを目指す。
上司と二人で出かけて、何を話せば良いのか分からず、言葉少なめだったが、そこは流石年上の余裕というべきか、沙耶が会話をリードしていた。
「そういえば、この間のお客さんって大丈夫だったの?」
「ああ、A社の件ですか。あれなら直接僕が現場に行って問題解決でしたよ」
「おお~さすが我が社のホープね」
とは言え、このように話題は仕事に関することがほとんどで、お互いの関係が発展する要素は全くなかった。
―40分後―
二人は目的地である糸島の白糸の滝に到着した。
まだ昼食前というのに、駐車場は車がズラリと並び、人も多かった。
「はぁ~、空気が美味しいね」

車を降りて背伸びをしながら沙耶がつぶやく。
福岡市内から車で1時間も経たないうちにマイナスイオンが溢れる滝を拝めるというのも、福岡の良い部分と言えるであろう。
「普段、仕事ばかりしていると、こういう自然って凄く良く感じますよね」
「おっ、君にもこの良さが分かるか。関心関心。」
二人は駐車場から滝に向かって歩いていく。
「先輩、昼食にはまだ早くないですか?」
「うーん、そうだねぇ。あ、あれしようよ」
沙耶が指をさしたのは「ヤマメ釣り」の看板。
そう、ここ糸島の白糸の滝ではヤマメ釣りを楽しむことが出来るのだ。
その為、夏休みの時期の7~8月は子ども連れのファミリーで溢れ返っているのだが、今はまだ7月前半ということもあって、幸い人は多くなかった。
裕もまた、幼い頃は父親に連れられて釣りに行く機会が多かったこともあり、ヤマメ釣りには興味を示した。
竿とエサをレンタルして釣り堀に向かうと、そこには形の良いヤマメが気持ちよさそうに泳いでいた。
「裕くん、エサつけてよ」
「自分で付けれないんですか?」
「付けれるけど、甘えてみようかと」
軽く舌を出して笑う彼女の姿は、決して職場では見れないものである。
『こういう先輩も悪くないな』
そんなことを思いながら、裕は慣れた手つきで針にエビを付けてあげた。
「ありがとう」
お礼を言って竿を受け取った彼女は、ポチャンと音を立てて川にハリを投げ込む。
すると1分も経たない内にヤマメがエサに食いつき、沙耶は難なく1匹目を釣り上げた。

釣り上げた魚を裕が掴み、ハリを外して再びエサを付ける。
「恋人」という関係でないために、もしかしたらこれは上司の我儘に付き合わされる部下の図かもしれない…。
再び、沙耶は2匹目を釣り上げる。
子どものようにはしゃぐ沙耶の姿を見て、裕は自分の胸が高鳴るのを感じた。
その後、二人は釣った魚をカウンターに持っていき、既に焼かれているヤマメと交換してもらった。ここ糸島の白糸の滝では、釣った魚を調理してもらえるわけではなく、その魚が焼き魚に交換される仕組みなのだ。もちろん、釣った魚を焼いてもらうこともできる。
「おじさん、昼食って何がお勧めですか?」
ヤマメを交換してもらう時に、沙耶が訪ねた。
「せっかくヤマメがあるんだったら流しそうめんがお勧めだよ」
「じゃあ、それで!」
沙耶は裕の意見も聞かずに決めてしまった。
正直、沙耶の行動は自分が中心であり、普通なら腹を立てる男性も少なくないだろう。
裕自身、まじめすぎる性格の為、本来なら沙耶の行動に苛立っても何ら不思議ではない。
しかし、普段はスーツに身を包み、厳しい口調で部下を叱り、他人が真似できないクオリティで仕事を終わらせる沙耶がロングスカートに黒のノースリーブ、その上に上品なカーディガンを羽織り、今まで見たことのない表情で笑う姿に裕は特別な何かを感じていたのだった。
その後、二人はヤマメを片手に流しそうめんを食べて、滝を満喫して車に戻った。

気付けば、時計の針は午後2時を指していた。
「先輩、この後どうするんですか?」
「え?白糸の滝に来たらあそこしかないでしょ」
そういって彼女はスマホを取りだし何かを検索して裕に見せた。
その画面に表示されていたのは「村上屋本舗 白雪」
福岡に住む人なら一度は聞いたことがあるであろう、かき氷の名店だ。
「あ~、これって糸島だったんですね」
「そうそう、凄く美味しいのよね」
そんな会話をしている内に5分ほどで白雪に到着した。
日曜の午後ということもあってか、15分ほど並んだが、二人は店内に入り、かき氷を注文した。
店内はほぼ満席だった為に、かき氷が運ばれてくるまでに時間がかかると思いきや、10分も経たないうちに裕にはイチゴかきごおりが、沙耶には宇治金時が運ばれてきた。

「へぇ、めっちゃ大きいんですね」
そう言いながら、裕はスプーンで氷をしゃくり、口に運ぶ。
氷なのにふわふわしている未知の食感に思わず声を上げる。
ふわふわしているにも関わらず、氷の持つシャキシャキ感は失われておらず、シロップは適度に氷と混ざり、絶妙の味を演出しているのが、白雪が人気店である最大の理由であろう。
「でしょ、ここの、本当に美味しいんだよね」
言葉から、沙耶が白雪に過去に来ていたことが伺える。
『前は誰と来たんだろう』
ふと、裕はそんなことを気にしていた。
「先輩は、何度か来たことあるんですか?」
「うん、同期と良く来ていたんだよね」
沙耶と一緒に、この場所に来た人物が女性であることが分かり、裕は何とも言えない安心感に包まれた。ただ、今朝まで沙耶のことを女性として意識していなかったこともあり「一時の感情の変化」と彼は自分を分析していたのだった。
とは言え、沙耶が裕を気に入っているように、裕も沙耶に対しては「美人で仕事の出来る上司」と前から認識しており、決して一時のものではないのだ。ただ、社内でも「美人上司」と多くが認識している彼女は、部下である裕にとって高嶺の花という存在だった。
だからこそ、今日、沙耶が自分を誘ってくれたのにも関わらず「男性として誘われているわけではない」とどこか自信を持てずにいたのだった。
つづく…